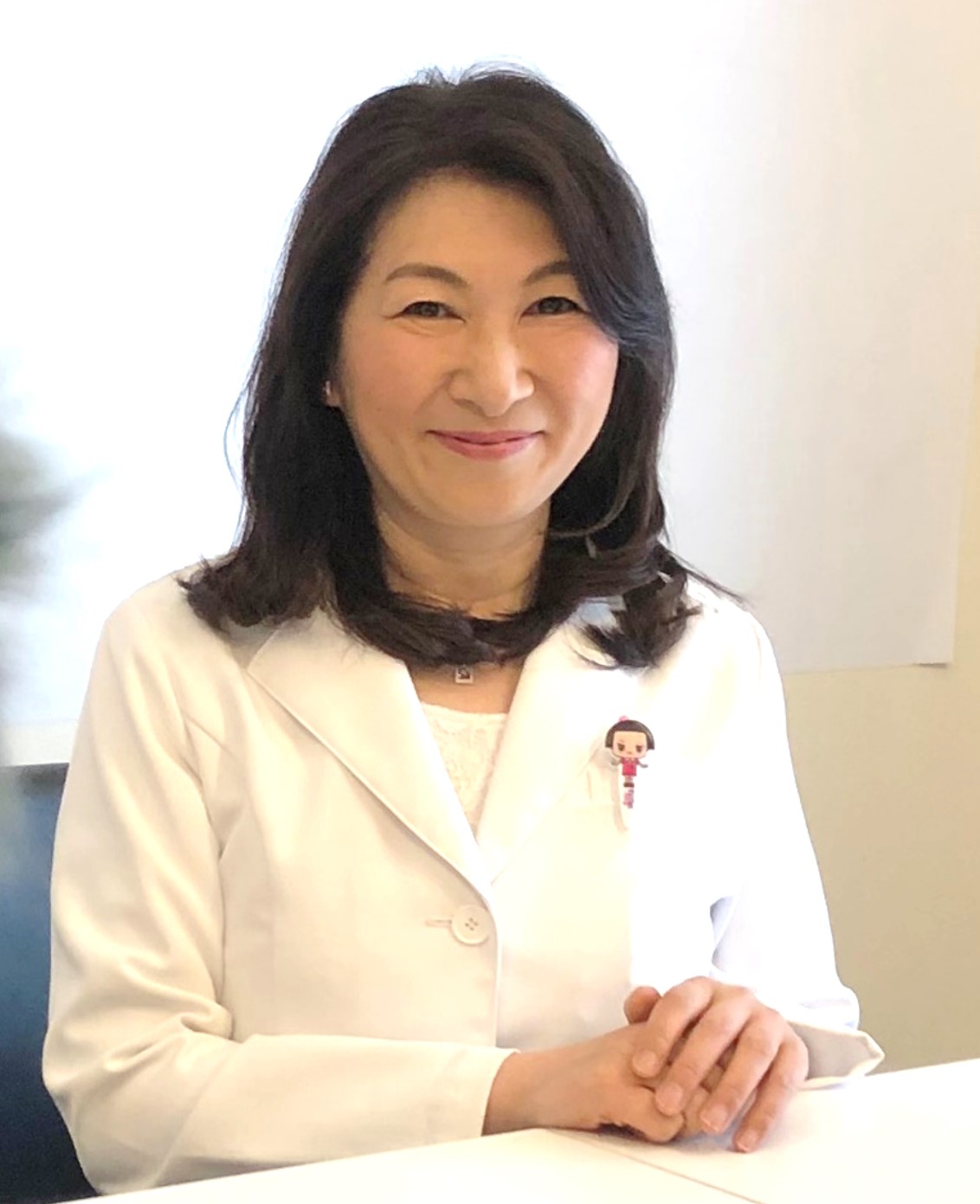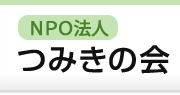
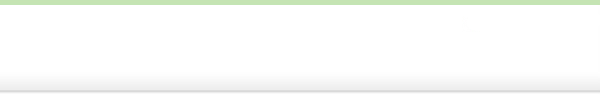
|
ホーム > 応援して下さる先生方 応援して下さる先生方つみきの会では、多くの専門家の先生方にゲスト会員になっていただいています。その中から、特にお世話になっている三人の先生をご紹介します。
井上雅彦先生プロフィール 鳥取大学大学院医学系研究科 臨床心理学講座 教授(応用行動分析学)井上先生ホームページ http://www.masahiko-inoue.com/ 井上先生の主な著書 「家庭で無理なく楽しくできる生活・学習課題46-自閉症の子どものためのABA基本プログラム」学習研究社、2008年 「自閉症支援-はじめて担任する先生と親のための特別支援教育」(井澤信三先生との共著)明治図書出版、2007年 「発達障害の子を育てる家族への支援」(柘植雅彦先生との共著)金子書房、2007年 井上先生からのメッセージ ABAは子どもさんを理解し、一人ひとりの子どもさんにあったかかわり方や学習の仕方を知るための、そしてなにより子どもさんのこころの扉をひらく鍵のようなものだと思います。ABAには長年の研究の中で科学的に証明されたさまざまな療育のエッセンス、つまり行動変容の原理があり、すぐれた技法が多く紹介されてきています。またこれらの知見はTEACCHプログラムやポーテージプログラムなど多くのプログラムに取り入れられています。しかし一つ一つのプログラムはすべてのお子さんにそのまま当てはまるものではなく、それぞれの子どもさんにあったアレンジが必要です。それにはABAの基礎的な原理を学ぶ必要があります。 つみきの会には、ABAを学んだ多くの先輩の親御さんやセラピストさんがおられ、子育てや療育の様々な疑問や悩みに、同じ目線から一緒に考えてくださいます。家庭でABAにもとづいた療育を続けていくコツは、子どもさん自身の、そして自分たちのペースで走っていくことだと思っています。同じ診断名やタイプの子どもさんでも、その時々の成長の時期によって学習のペースは違いますし、変わってきます。会の中には自分や自分のお子さんと同じペースで走っている仲間がきっと見つかるはずです。つみきの会がそんな出会いの場になれば、そして私もその中でお手伝いができればと考えています。 
安原昭博先生プロフィール 小児科医、安原こどもクリニック院長、YCCこども教育研究所代表理事,関西医科大学小児科非常勤講師安原先生のホームページ http://www.y-c-c.jp/index.html 安原先生の主な著書 「ADHD・LD・アスペルガー症候群かな?と思ったら…」明石書店、2007年 安原先生のメッセージ 1997年に藤坂さんとお会いして自閉症に対するABA(行動療法)のことを知りました。すでに12年がたちます。初めて行動療法の関係の本を読んだのはキャサリン・モーリスの「わが子よ、声を聞かせて-自閉症と闘った母と子-」でした。私は、自閉症は治らないと教えられていたので大変興味深く読んだのを覚えています。 その後、行動療法による治療を考え直し、自閉症を治そうと試みるようになりました。ローバースの行動療法だけでなく、応用行動分析や種々の治療法について勉強を始めるきっかけになりました。そのころに出会った自閉症の子ども達は、すでに中学生、高校生になっています。子ども達はそれぞれ立派に成長されています。現在、自閉症は治らなくても、とても改善し得るものであると確信しています。 自閉症は病気というよりも特徴ある性格なのではないでしょうか。少しでも現代社会で過ごしやすく成長するように教育してあげるべきと思います。ABA(行動療法)は自閉症だけでなく、すべての子ども達を健やかに成長させるための教育方法の一つであり、教育の根底にある方法と考えられます。つみきの会の皆さん、あきらめないでがんばってください。私たちもできる限りのお手伝いはします。 星野恭子先生プロフィール昌仁醫修会 瀬川記念小児神経学クリニック 理事長 東邦大学大森病院第一小児科にて研修、関東の病院にて勤務後、2000年、旧瀬川小児学クリニック研修中に早起きサイトを結成。全国での講演や和歌山県教育委員会はじめ地方自治体のパンフレット作成や啓発活動に協力、2013年に文部科学大臣表彰を受賞した。 2005年早稲田大学にて時計遺伝子研究を経て、2010年から和歌山県南紀の南和歌山医療センターに勤務。2014年瀬川昌也院長先生が御逝去されたことから、2015年小児神経学クリニック院長に就任。 2018年8月、第28回 日本外来小児科学会で発表した「生後3〜4か月の睡眠リズムの確立と自閉スペクトラム症(ASD)の発症について〜小児神経専門クリニックにおける検討」が優秀演題賞を受賞。2021年1月、今までの医療、全国での講演、地域医療への貢献が評価され「第9回日本医師会赤ひげ大賞」において、赤ひげ功労賞受賞。臨床研究を中心とした睡眠の啓発活動の拠点を目指している。 星野先生のメッセージ つみきの会代表の藤坂先生とは、長いお付き合いになります。 20年前に、つみきの会を知り、藤坂先生の勉強会にも参加させて頂きました。 また10年前、私が南和歌山医療センターに勤務中に、南紀の患者さんにもABAを知ってもらおうと藤坂先生に無理をお願いして、ご指導を頂いております。 さらに、私が現職になったときも、また無理をお願いして、2か月に1度、ABA外来を担当していただき、本当に感謝しております。 当院では、医師や心理士が、藤坂先生のABAを見学し、学ばせていただいており、本当に助かっております。 もちろん、私も、日々の小児神経の外来でABAのエッセンスを取り入れています! 「嫌なことがあるとパニックします」「叩いてきます」等の相談は日常茶飯事。「言葉が出ない」「真似をしない」「言うことを聞かない」等、保護者の皆さんの悩み事は尽きません。 そこで、最も大事な指導方法が、ABA、すなわち応用行動療法です。 私の印象ではありますが、保護者の皆さんが一番出来ないのは「無視すること」と「褒める」こと。わざと大声を出す、叩く等の場合、「やめなさい」「うるさい」「どうしてそんなことするの」と言います。不適切な対応ですが、消去は難しいですよね。結局、うるさいからと、本人の言いなりになってしまう・・徹底無視は、なかなか難しいのが現状ですね。 もう一方で、褒めるのもできていらっしゃいません。私は、自分の外来で、真似の練習を、私がABAを使ってしてみせています。「できた!」「上手!」の声かけのタイミングと大きな声や拍手に唖然としているご両親。ご両親を振り返り、「こんな感じで褒めてね」と私が声をかけると「あ、、、はい、、、(汗)」とたじたじ、、っというご様子です。当院にいらっしゃった方は思い当たるのではないでしょうか。 「褒める」ことは、前頭葉機能を刺激します。「消去」もとても重要です。ぜひ、ABAのエッセンスを理解して、日々の生活に応用してください。 |